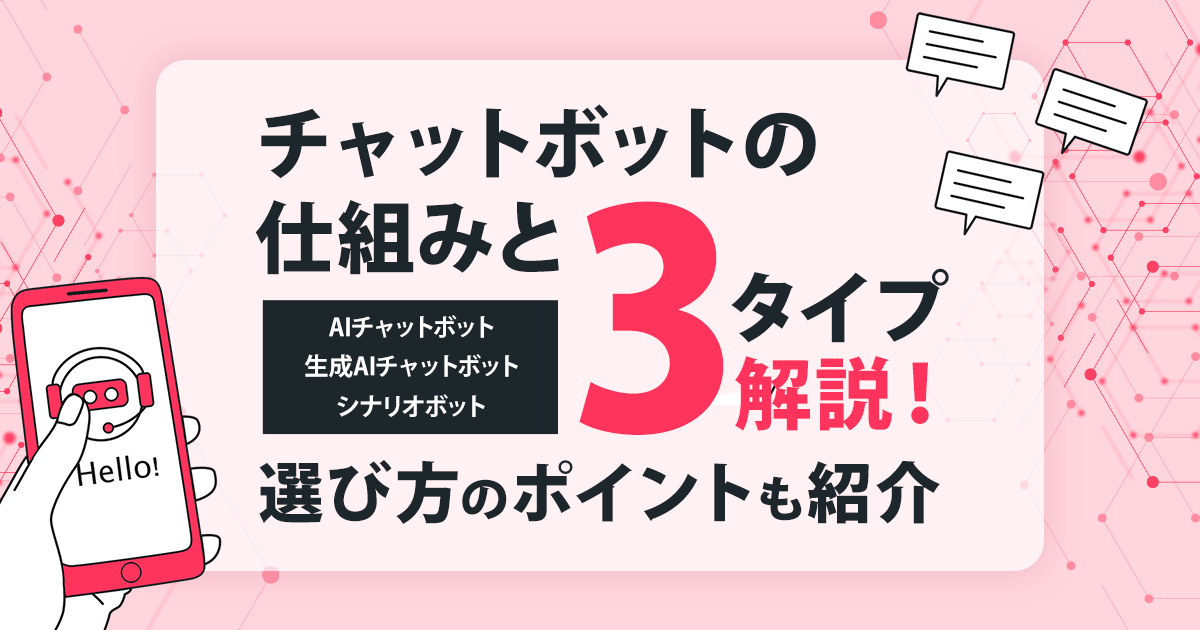チャットボットを導入しても、応答の精度が低く、ユーザーとの自然な対話が難しいという課題を抱える企業は少なくありません。
特に自由入力への対応では、ユーザーの意図を正しく理解できないケースも目立ちます。
チャットボットで効果的な自動対話を実現するには、その基本的な仕組みを理解しなければなりません。
各タイプの動作原理や特徴を把握すれば、より適切な選択と運用が可能になります。
本記事では、チャットボットの基本的な仕組みから、AIやシナリオ型などの各タイプの特徴、具体的な機能まで、実務で活用できる情報を分かりやすく解説します。
チャットボットを事業に効果的に活用したい方は、ぜひ参考にしてください。

チャットボットとは?
チャットボットとは、人間に代わってテキストや音声による会話を自動的に行うプログラムです。
「チャット(Chat)」と「ロボット(bot)」を組み合わせた言葉で、Webサイトやスマホアプリを通じて、顧客との対話を自動化してくれます。
例えば、企業のWebサイトでの問い合わせ対応や、LINE公式アカウントでの案内、さらにはSiriやAlexaのようなAIスピーカーまで活用されるようになりました。
チャットボットの活用場面は、主に以下の3つが挙げられます。
| 社内ヘルプデスク | 社内規定の確認、IT関連の問い合わせ対応 |
| カスタマーサポート | 製品の使い方案内、よくある質問への回答 |
| マーケティング支援 | 商品レコメンド、キャンペーン情報の提供 |
チャットボットの導入により、顧客は24時間いつでも必要な情報を得られ、企業側も問い合わせ対応の効率化や人件費の削減できるメリットがあります。
近年では技術の進歩により、より自然な会話が可能になり、企業のデジタル化を助けるツールとして注目を集めています。
チャットボットの進化
チャットボットの進化は、1966年に開発された「ELIZA(イライザ)」から始まります。ELIZAは英語での会話に対応した初めてのチャットボットで、心理カウンセラーのような応答を行うプログラムでした。
日本でもチャットボットの歴史は古く、1980年代初頭のパソコン普及期には、すでに基本的な会話が可能なプログラムが存在していました。
その後、インターネットの普及とAI技術の発展により、チャットボットは徐々に進化を遂げていきます。
特に大きな転換点となったのが、2022年11月30日のChatGPTの登場です。ChatGPTは従来のチャットボットとは一線を画す性能を持ち、わずか2か月で1億人のアクティブユーザー数を記録する急成長を遂げました。
その後の生成AI分野の主な進展は、以下のとおりです。
| 2023年3月1日 | ChatGPTのAPI版が公開 |
| 2023年3月15日 | GPT-4の登場 |
| 2023年前半 | GoogleのBard、MicrosoftのBingなど続々登場 |
| 2023年11月6日 | カスタマイズ可能なGPTsがリリース |
生成AIの急速な進化は、チャットボット市場にも大きな変化をもたらしています。
従来型のAIチャットボットに加えて、生成AI型の新しいチャットボットが登場し、より自然で柔軟な対話が可能になりました。
特に企業での活用では、単純な問い合わせ対応だけではなく、業務効率化や新しいサービス創出など、その可能性は大きく広がっています。
チャットボットが注目される理由
チャットボットが注目される背景には、企業の人材不足と、顧客からの24時間対応への要望の高まりがあります。
特に以下の3つの要因が、チャットボット導入を加速させています。
| 人材不足 | カスタマーサポート担当者の採用難 応対品質の標準化が困難 |
| コスト削減 | 人件費の上昇 24時間対応の運営負担 |
| 顧客ニーズ | 即時回答への期待 スマートフォンでの問い合わせ増加 |
チャットボットを導入すれば、企業は以下のような効果を得られます。
まず、24時間365日の自動応対により、夜間や休日の問い合わせにも対応できます。人手では難しい常時対応が可能になり、顧客満足度の向上につながるでしょう。
次に、定型的な問い合わせの自動化により、サポート担当者の業務負荷を軽減できます。
さらに、AIやシナリオに基づく一貫した応対により、サービス品質の標準化も実現できます。
担当者による対応品質のばらつきを抑え、安定したサービスを提供できるでしょう。
チャットボットは、人材不足やコスト削減のような企業の課題解決と、迅速な対応を求める顧客ニーズの両方に応えられるツールとして、今後さらに注目が高まるでしょう。
チャットボットの仕組み
チャットボットの仕組みは、人間とコンピュータの間で行われる会話を自動化するための一連のプロセスです。基本的な動作の流れを理解すれば、より効果的な活用方法が見えてきます。
チャットボットには以下のような基本機能が備わっています。
| 自然文応答 | 通常の会話のような文章での返答 |
| 選択肢提示 | ボタンやメニューによる選択式の応答 |
| 有人切替 | 複雑な質問を人間のオペレーターへ転送 |
| システム連携 | 予約システムやECサイトとの連携 |
チャットボットが応答を返すまでの基本的な仕組みは、以下の3つのステップで構成されています。
- ユーザーが入力した質問文から重要な単語や意図を抽出
- 抽出したキーワードに関連する最適な回答を探索
- 検索結果を自然な日本語の文章に変換
AI型チャットボットの場合は、これらの処理に機械学習が加わり、会話を重ねるごとに応答の精度が向上します。ユーザーの質問意図をより正確に理解し、適切な回答を提供できるようになるでしょう。
チャットボットの仕組みを理解した上で、次は現在主流の3つのタイプに関して詳しく見ていきましょう。
チャットボットの主な3タイプ
チャットボットは、使用する技術や運用方法によって3つのタイプに分類できます。
それぞれに特徴があり、用途に応じて使い分けることが大切です。
| 主な特徴 | 得意な用途 | |
| AIチャットボット(従来型AI) | 学習済みデータを活用し、正確な応答を生成 | 定型的な問い合わせ対応 |
| 生成AIチャットボット | ChatGPTのような生成AIを活用し、柔軟な対話を実現 | 複雑な質問への対応 |
| シナリオボット | あらかじめ設定したシナリオに沿って応答 | 商品案内や予約受付 |
どのタイプを選ぶかは、導入の目的や予算、運用体制によって判断する必要があります。
チャットボットの3つのタイプと費用相場
チャットボットの3つのタイプには、それぞれ特徴的な仕組みと活用方法があります。導入目的に応じて最適なタイプを選択するようにしましょう。
| AIチャットボット(従来型) | 生成AIチャットボット | シナリオボット | |
| 入力方式 | 自由入力 | 自由入力 | ボタン選択が中心 |
| 応答の特徴 | 事前チェック済みの正確な回答 | 柔軟な文章を動的に生成 | 設定済みシナリオに沿った回答 |
| 導入コスト | 月額10~60万円 | 月額10~100万円 | 月額3~15万円 |
それぞれのタイプの特徴をまとめると、以下のとおりです。
| 仕組みの特徴 | 主な用途 | |
| AIチャットボット(従来型AI) | AIが投稿文全体を認識し、最適な応答を選択事前チェック済みの回答のみを使用自由入力に対して柔軟に対応 | ホームページの問い合わせ対応医療や契約内容など、正確性が重視される分野カスタマーサポート業務 |
| 生成AIチャットボット | ChatGPTなどの生成AIを活用学習データとプロンプトを基に回答を生成予期せぬ質問にも柔軟に対応 | 社内FAQシステム問い合わせ返信の下書き作成データ分析や整理業務 |
| シナリオボット | ツリー構造による選択式の対話If-Thenルールで動作を設定予め定義された範囲内で応答 | 製品・サービスの診断ツールマーケティングでの顧客誘導定型的な案内業務 |
各タイプには明確な特徴があり、それぞれが得意とする用途が異なります。
例えば、正確性を重視する場合は従来型AI、柔軟な対応を重視する場合は生成AI、シンプルな案内業務には シナリオボットが適しています。
チャットボットの主な機能
チャットボットは、企業の業務効率化やカスタマーサービス向上につながるさまざまな機能を備えています。
ここでは、チャットボットの基本的な機能や分野別の活用例を紹介していきます。
基本的な機能
チャットボットには、企業の業務効率化やカスタマーサービス向上につながるさまざまな機能が搭載されています。
主な機能には、以下のようなものが挙げられます。
| FAQ対応 | よくある質問への自動回答テンプレート回答の登録と管理 |
| 予約管理 | 空き状況の確認予約の受付と変更リマインド通知の送信 |
| リード獲得 | 問い合わせフォームへの誘導顧客情報の収集資料請求の受付 |
| カスタマーサポート | 製品やサービスの問い合わせ対応有人対応への自動振り分けチャット履歴の保存と分析 |
| マーケティング支援 | 商品レコメンドキャンペーン情報の案内ユーザー行動の分析 |
それぞれの機能は単独でも効果を発揮しますが、複数の機能を組み合わせることで、より高い成果を上げられます。
例えば、FAQ対応とカスタマーサポートを連携させれば、基本的な質問は自動で処理しながら、複雑な問い合わせのみを人間のオペレーターが対応するといった効率的な運用も可能になるでしょう。
分野別のチャットボット
チャットボットは業界や分野によって求められる機能や活用方法が異なります。
それぞれの分野での特徴的な活用事例を見ていきましょう。
| ECサイト | 商品検索のサポート購入方法の案内よくある質問への回答在庫状況の確認 |
| 飲食業 | メニューの詳細説明予約の受付管理アレルギー情報の提供クーポン情報の案内 |
| 医療業界 | 初期症状の確認診療予約の調整診療科目の案内医療費の説明 |
| 教育分野 | 学習内容のサポート授業スケジュールの案内入学案内や資料請求保護者からの問い合わせ対応 |
各分野の特性や顧客ニーズに合わせてチャットボットの機能を活用すれば、より効果的な活用が可能になります。特に近年は、AIの進化により、より専門的な内容にも対応できるようになってきています。
チャットボットを選ぶポイント
チャットボットを導入する際は、自社のニーズや目的に合わせて最適なタイプを選択する必要があります。以下のチェックリストを参考に、自社に適したチャットボットを見極めましょう。
| AIチャットボット | 生成AIチャットボット | シナリオボット | |
| 自由入力に対応したい | ○ | ◎ | × |
| 初期費用を抑えたい | △ | △ | ◎ |
| 正確性の高い応答が必要 | ◎ | ○ | × |
| カスタマイズ性を重視したい | ○ | ◎ | △ |
このようなチェックリストも活用できますが、実際の導入に向けては、より具体的な目的の明確化が必要です。
ここでは、チャットボットを選ぶポイントをさらに詳しく説明します。
目的を明確化する
チャットボットの目的を明確にしないまま導入を進める企業は少なくありません。
「業務効率化のため」「顧客満足度向上のため」といった漠然とした理由だけでは、期待する効果を得られない可能性があります。
目的は具体的な数値目標として設定しましょう。
例えば「問い合わせ対応時間を30%削減する」「夜間の問い合わせ対応率を100%にする」「リード獲得数を20%増加させる」といった具体的な目標設定が必要です。
目的を数値化すれば、導入後の効果測定が簡単にでき、予算配分や運用体制の検討もスムーズに進められます。費用対効果の高いチャットボット導入を実現するためには、まず目的の明確化から始めるようにしましょう。
費用と運用体制を検討する
チャットボットの導入には、適切な予算設定と運用体制の構築が欠かせません。特に初期費用とランニングコストのバランス、そして運用の簡易性を考慮する必要があります。
例えば、月額3~15万円程度で始められるシナリオボットは、マーケティング目的の企業に適しています。
一方、顧客対応の効率化を目指す企業なら、月額10~60万円のAIチャットボットが最適でしょう。
また、より柔軟な対応を求める企業には、月額10~100万円の生成AIチャットボットがおすすめです。
運用体制では、チャットボットの回答内容を定期的に見直し、精度を向上させる担当者の確保が必要です。
複雑な問い合わせに対応するオペレーターの体制も整える必要があります。
このように、目的に合わせた予算と運用体制を検討した上で、適切なチャットボットを導入すると良いでしょう。
まとめ
チャットボットは、人間とコンピュータが対話を行うプログラムであり、その仕組みは大きく3つのステップで動作します。ユーザーの入力を認識し、データベースから最適な回答を検索し、それを自然な形で表示するという流れです。
この基本的な仕組みは、AIチャットボット、生成AIチャットボット、シナリオボットといった各タイプで異なる特徴を持ちます。
従来型のAIは事前に用意した回答から最適なものを選択し、生成AIは自由な回答を生成し、シナリオボットは決められたフローに沿って応答します。
チャットボットの仕組みが理解できれば、自社の用途に合わせた適切な選択が可能になります。
必要な機能や予算を考慮しながら、最適なタイプのチャットボットを選び、効果的な活用を目指しましょう。
▼株式会社エフ・コードでは、WEBチャットボットツール「sinclo」を提供しています。
以下のボタンから「sinclo」の概要資料を無料でダウンロードいただけます。
「sinclo」の主な特長は以下のとおりです。
・チャットツリー設定(ツリー形式で直感的にチャットボットの設定が可能)
・無人チャットと有人チャットのハイブリッド型
・多種多様な外部サービス連携
・一括ヒアリング(署名整形)機能
・1契約で複数のサイトに無制限で設置が可能
各機能の詳細や導入に関するお問い合わせなど、お気軽にご相談ください。

![[ロゴ] 株式会社エフ・コード](/assets/img/layout/header_title.svg)