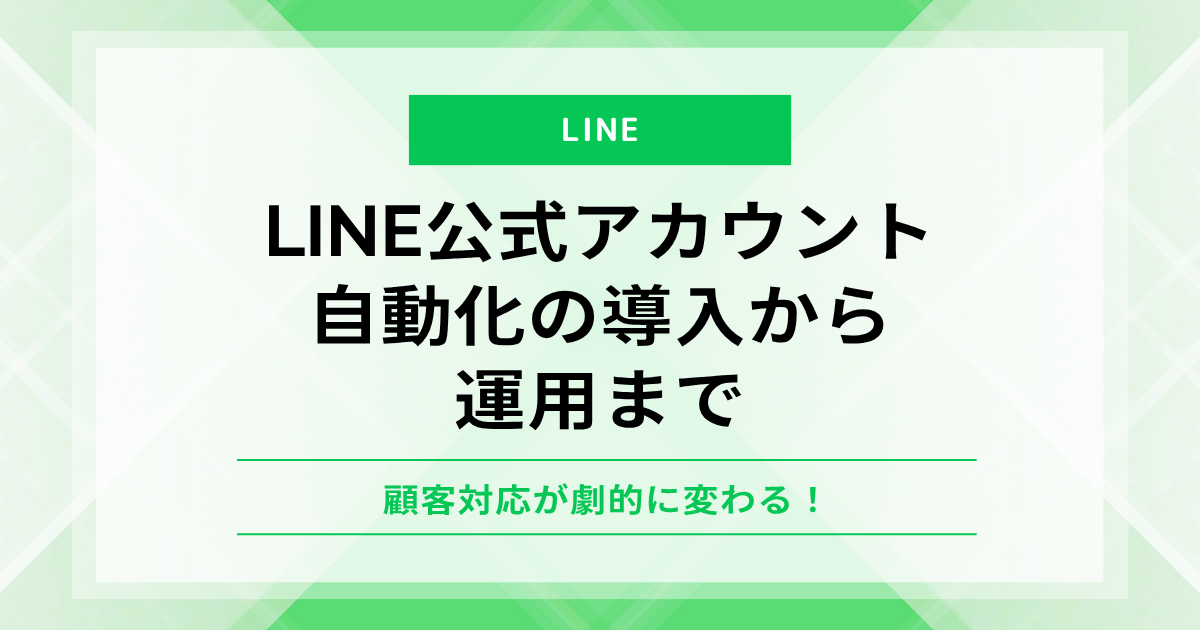LINE公式アカウントの運用を始めてみたものの、思うような成果が出ずに悩んでいる企業や店舗が急増しています。実は、運用を断念した企業の78%が「友だちが集まらない」ことを最大の理由として挙げており、この課題は多くの運用者に共通する悩みです。
本記事では、実際の失敗事例から見えてきた典型的なパターンを整理しました。飲食店で友だち獲得目標100人に対して実績わずか10人という厳しい現実から、毎日配信によるブロック率18.4%という痛い教訓まで、具体的な事例をもとに改善策を提示します。
重要なのは、これらの失敗には明確な原因があり、適切な対策を講じることで必ず改善できるということです。本記事を通じて、あなたのLINE公式アカウントが陥りやすい罠を事前に回避し、効果的な運用への道筋を見つけていただければ幸いです。

友だち獲得でつまずく典型的なパターンと改善策
LINE公式アカウントを開設したものの、思うように友だちが集まらない。これは多くの運用者が最初に直面する大きな壁です。実際、運用を諦めた企業の78%が「友だちが集まらない」ことを最大の理由として挙げています。友だち獲得の失敗には明確なパターンが存在し、その原因を理解することで劇的な改善が可能です。
ここでは、単純なQRコード設置の落とし穴、特典設計の重要性、そして意外と見落とされがちな声かけの効果について、実際の失敗事例と成功事例を交えながら解説していきます。
出典:LINEヤフー for Business | 公式note、始めました。「LINE公式アカウントの運用「失敗」の最大の理由をやっつけよう!」
「とりあえずQRコード」では集まらない
多くの店舗が陥る最初の失敗が、「QRコードを設置すれば友だちが増える」という安易な考えです。ある飲食店では、レジ横にPOPを掲示し、スタッフが口頭で案内していましたが、1カ月の目標100人に対し、実際は10人程度しか集まりませんでした。
この失敗の原因は、顧客の立場に立った動線設計ができていないことです。QRコードを見ても、その場で登録する理由がなければスルーされてしまいます。
効果的な設置場所は、商品パッケージ、レシート、カウンター周り、デジタルサイネージなど、顧客が立ち止まる場所です。さらに「友だち追加で今すぐ使える500円クーポン」など、具体的なメリットを明記することが重要です。
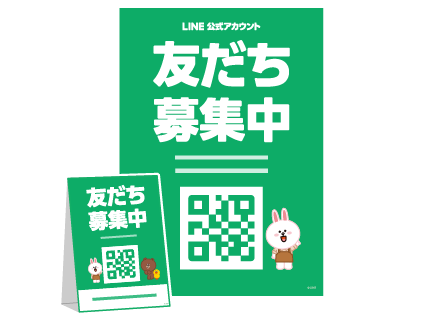
単なるQRコードの設置から、顧客の行動を促す仕組みづくりへ。この視点の転換が、友だち獲得成功への第一歩となります。
出典:assist「【LINE公式アカウント】LINE運用をする上で、こんな失敗をしていませんか? ~失敗から学ぶ、成功への近道~」
特典設計のミスが招く登録率の低迷
友だち追加特典の設計ミスも、獲得率を大きく左右します。「友だち追加で情報をお届けします」という漠然とした訴求や、使用期限が短すぎるクーポンでは、登録への動機付けが弱くなります。
実際、クーポンの使用期限が短すぎる場合、約70%のユーザーが使用を諦めてしまうというデータがあります。
効果的な特典設計のポイントは、
- 即時性のある特典(今すぐ使える)
- 具体的な価値の提示(500円OFF、ドリンク1杯無料)
- 適切な有効期限(最低2週間以上)
- 継続的なメリット(毎月1日にクーポン配布)
です。
ある業務用スーパーでは、「通常1個100円の商品が2個で100円」という明確な特典を提示し、1年間で友だち数8,000人を達成しました。特典の価値を明確に伝えることが、登録率向上の鍵となります。
出典:Lステップ「LINE公式アカウントでありがちな失敗事例とは?」
声かけ・告知方法の工夫で獲得率を向上させる方法
スタッフによる声かけは、正しく行えばもっとも効果的な友だち獲得方法です。しかし、多くの店舗では「LINE始めました」と伝えるだけで、実際の登録につながっていません。
成功している店舗では、「お友だちになるとキャンペーンのお知らせが届くので、よろしければ今お友だちになっていただけますか?」といった具体的なメリットを含めた提案を行っています。
タイミングも重要で、会計時ではなく、商品を待っている時間や席に着いてメニューを見ている時間など、余裕のあるタイミングを選びます。
また、自社ウェブサイト、メールマガジン、SNS投稿など、既存の顧客接点すべてでLINE公式アカウントの告知を行うことで、友だち追加の機会を最大化できます。声かけから始まる小さな改善が、大きな成果につながります。
■オンラインでの主な友だち追加施策

引用元:LINE Official Account Manager内「友だち追加ガイド」
配信コンテンツの質で失敗する理由と対処法
友だちを獲得できても、配信内容が原因でブロックされてしまっては元も子もありません。多くの企業が陥る配信の失敗には、共通する問題点があります。なぜユーザーは配信を「うざい」と感じ、ブロックしてしまうのでしょうか。
ここでは、配信コンテンツで失敗する3つの典型的なパターンとして、宣伝過多の危険性、セグメント配信の重要性、そして成功企業が実践している情報配信の黄金比について、データと事例を交えてご紹介します。
宣伝ばかりでブロック率18.4%の悲劇
LINE公式アカウントは便利な宣伝ツールですが、宣伝に偏りすぎるとブロック率が急上昇します。毎日配信している飲食アカウントの平均ブロック率18.4%という数値が、その危険性を物語っています。
顧客の8割が「必要な情報のみを受け取りたい」と考えているのに、多くの企業が販促メッセージを頻繁に配信してしまっています。これは、テレビ番組でCMが多すぎるとチャンネルを変えてしまうのと同じ心理です。
成功している企業は、週1回の配信を基本とし、キャンペーン時のみ頻度を上げています。また、配信時間帯もターゲット層のライフスタイルに合わせて設定することが重要です。
宣伝だけでなく、顧客にとって価値のある情報を提供することで、ブロック率を大幅に改善できます。
出典:SocialPlus「LINE公式アカウントのブロック率とどう向き合うか?〜商材、配信頻度・配信方法・友だち数別の調査結果からわかること」
セグメント配信を使わない機会損失
属性を無視した一斉配信は、「自分には関係ない」と感じさせ、エンゲージメントを低下させます。しかし、セグメント配信機能を使いこなせている企業は全体のわずか30%程度です。
あるアパレルブランドの失敗例では、10代向け商品を50代に配信するなど、的外れなターゲティングが多く見られました。
LINE公式アカウントでは、年齢、性別、居住地域などの属性情報や、過去の購買履歴、クリック履歴に基づくセグメント配信が可能です。これにより、各ユーザーに最適化されたメッセージを届けることができます。
自社サービスの会員IDとLINEを連携し、アンケートで詳細な属性情報を収集することで、より精度の高いターゲティングが実現できます。
出典:J-Barrel「元運用者が語る!LINE公式アカウントでやりがちな失敗と対策方法」
有益情報と販促のゴールデンバランス
配信成功の鍵は、有益情報7割、販促3割のバランスです。有益な情報とは、季節に応じた商品の使い方、業界トレンド、プロの裏技、顧客の悩み解決法などです。
また、「〇〇しないと損します!」といったあおり調のコピーは避け、ブランドイメージに合った親しみやすい文体を心がけることが大切です。
顧客との信頼関係を構築することで、長期的な関係性を築けます。販促一辺倒ではなく、顧客の立場に立った情報提供を心がけることが、ブロック防止と売上向上の両立につながります。
顧客対応で信頼を失う危険な落とし穴
LINEでの顧客対応は、従来のメールや電話とは異なる特性があり、その違いを理解していないと大きな失敗につながります。一度失った信頼を取り戻すのは、新規顧客を獲得するよりもはるかに困難です。
ここではLINE特有の顧客対応における3つの落とし穴として、返信スピードの重要性、自動応答の適切な設定方法、そしてピンチをチャンスに変えるクレーム対応術について、実践的なノウハウをお伝えします。
返信遅延が招く顧客満足度30%への転落
LINEは即時性の高いツールとして認識されているため、返信の遅れは致命的です。調査によると、1時間以内の返信で顧客満足度は95%、24時間を超えると30%まで低下します。
顧客の85%が24時間以内の返信を期待している中、迅速な対応体制の構築は必須です。しかし、24時間365日の即時対応は現実的ではありません。
解決策は、営業時間内の迅速な有人対応と、営業時間外の自動応答の組み合わせです。自動応答で一次対応を行い、「翌営業日に詳しくご連絡します」と明記することで、顧客の不安を軽減できます。
返信時間の短縮は、顧客満足度向上のもっとも確実な方法です。まずは営業時間内の1時間以内の返信を目標に、体制を整えることから始めましょう。
出典:J-Barrel「元運用者が語る!LINE公式アカウントでやりがちな失敗と対策方法」
自動応答の設定ミスが生む不信感
自動応答は便利ですが、設定ミスは顧客の不満を招きます。ある便利屋では、個別チャットのみで自動応答を活用せず、営業時間外の問い合わせに対応できませんでした。結果、「問い合わせを無視された」という苦情が相次ぎました。
効果的な自動応答には、営業時間の明確な表示、問い合わせ確認の通知、対応までの想定時間、代替連絡手段の案内、よくある質問へのリンクが必要です。
特に重要なのは、機械的でない親しみやすい文体です。「お問い合わせありがとうございます」「申し訳ございませんが」といった丁寧な表現で、顧客に安心感を与えます。
自動応答は顧客対応の補助ツールです。設定を工夫することで、営業時間外でも顧客満足度を維持できます。
出典:assist「【LINE公式アカウント】LINE運用をする上で、こんな失敗をしていませんか? 〜失敗から学ぶ、成功への近道〜」
クレーム対応をチャンスに変える5ステップ
クレーム対応は、適切に行えば顧客との関係を強化するチャンスです。LINEでのクレーム対応には独特の難しさがありますが、以下の5つのステップで効果的に対応できます。
- 1.迅速な初期対応:LINEの即時性を考慮し、1時間以内に「お困りの件、承りました」という一次返信を行う
- 2.感情への共感:「ご不便をおかけして申し訳ございません」など、顧客の感情に寄り添った丁寧な言葉遣いで対応する
- 3.解決策の提示:具体的な改善策を複数用意し、顧客に選択肢を与えることで主体性を尊重する
- 4.進捗の報告:対応状況を小まめに報告し、「現在確認中です」「あと30分ほどお時間をいただきます」など透明性を保つ
- 5.アフターフォロー:問題解決後も「その後いかがでしょうか」とフォローし、再発防止策を伝える
LINEでは、簡単な問い合わせはチャットボットで対応し、感情的な問題や複雑なクレームは速やかに有人対応に切り替えることが重要です。適切なクレーム対応により、通常の顧客よりもロイヤルティの高い顧客に転換できる可能性があります。
データ活用不足が招く運用の迷走
「効果があるのか分からない」まま運用を続けている企業が驚くほど多いのが現状です。データを見ずに運用することは、羅針盤なしで航海に出るようなもの。成功企業と失敗企業の差は、まさにこのデータ活用にあります。
データ活用における3つの重要ポイントとして、運用開始前に必ず設定すべきKPI、日々チェックすべき基本指標、そして意外と見落とされがちな競合分析の手法について、実践的なアプローチをご紹介します。
KPI設定なしで始める危険性
多くの企業が「みんなが使っているから」という理由でLINE公式アカウントを始めます。しかし、明確な目的とKPIがないと、手探り状態が続き、成果が上がらず運用をやめてしまいます。
ある雑貨屋では、目的を明確にせず場当たり的な配信を繰り返し、結果として何も成果が得られませんでした。
効果的なKPI設定には、まず自社の課題を洗い出すことが重要です。新規顧客獲得、リピーター育成、対応効率化など、具体的な目的を設定し、それらに対応した友だち数の目標、開封率、CTR、コンバージョン率、ブロック率上限などの数値目標を決めます。
業種や目的により重要指標は異なります。ECサイトならコンバージョン率、実店舗なら来店促進率が重要です。明確なKPIがあれば、運用の方向性が定まり、改善点も見えてきます。
出典:assist「【LINE公式アカウント】LINE運用をする上で、こんな失敗をしていませんか? 〜失敗から学ぶ、成功への近道〜」
開封率・CTRを見ない運用の末路
データを見ずに運用することは、目隠しで車を運転するようなものです。多くの企業が「送れば来店するはず」という短絡的な考えで運用を続けています。
基本的な分析指標として押さえるべきなのは、配信数と到達率、開封数と開封率、クリック数とCTR、ブロック数とブロック率です。これらの数値を定期的にチェックし、改善策を実施することが重要です。
開封率が低い場合は配信時間やメッセージ冒頭文の見直し、CTRが低い場合はコンテンツ内容やCTAボタンの配置改善が必要です。
まずは月1回の定期的なデータチェックから始め、徐々に分析頻度と深度を上げていくことをおすすめします。データなくして改善なし。この原則を忘れずに運用しましょう。
競合分析を怠ることのリスク
自社データ分析だけでなく、競合他社の動向把握も重要です。多くの企業が競合分析を怠り、独自性のないコンテンツでブロック率が上昇しています。
競合分析で確認すべきポイントには、配信頻度とタイミング、キャンペーン内容、リッチメニューデザイン、友だち獲得施策、クーポン内容などがあります。
例えば、競合が週2回配信なら、自社は週1回の質の高い配信に特化するという差別化戦略が可能です。
また、他業界の成功事例も参考になります。あるスポーツ教室では、月1回の見学会で既存ユーザーの口コミを活用し、来場者の7割が入会という成果を上げています。業界の枠を超えた学びが、新たな施策のヒントになります。
出典:Lステップ「LINE公式アカウントでありがちな失敗事例とは?」
LINE公式アカウントを導入したものの、日々の配信が作業になってしまい、売上や集客といった本来の成果に繋がっていないと感じてはいませんか?自社にとって本当に必要な機能の選定や、客観的なデータに基づいた改善策の立案は、多くの担当者様が直面する大きな壁です。
そこでお役立ていただけるのが、運用の健全性を一目で診断できる「LINE公式アカウント運用中チェックリスト10」を収録した実践ガイドです。
成果を出すために不可欠な設定から、配信の質を高めるための改善指標まで、自己流の運用を脱して「勝てる運用」へとシフトするためのノウハウを凝縮しました。今の施策に限界を感じている方、次の打ち手に悩む方の指針として、ぜひ本資料をご活用ください。
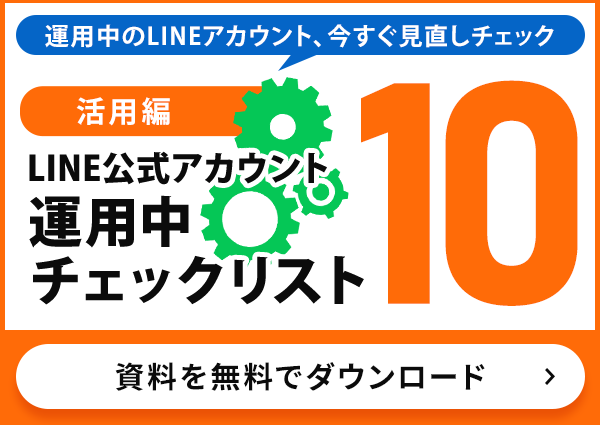
新たな失敗リスクと対策
2024年以降、LINE公式アカウントの運用環境は大きく変化しています。法規制の強化、新機能の登場、AI技術の進化など、これまでとは異なる新たなリスクと機会が生まれています。
今後の運用で特に注意すべき3つのポイントとして、法的リスクを回避するための対応策、競合に差をつける新機能の活用法、そしてAIツール導入時の注意点について、最新の情報をもとにお伝えします。
個人情報保護法改正への対応遅れ
2024年4月施行の改正個人情報保護法により、より厳格な個人情報の取り扱いが求められています。多くの企業が対応に遅れ、法的リスクを抱えたまま運用を続けています。
具体的に対応が必要な項目として、属性情報収集時の同意取得プロセスの明確化、取得情報の安全管理体制構築、プライバシーポリシーの更新と周知が挙げられます。
特にアンケート機能での属性情報収集では、利用目的を明確に示し、明示的な同意が必要です。データの保管期間や削除方法も明確にし、顧客に開示する必要があります。
対応を怠ると、個人情報漏えいによる炎上だけでなく、行政処分や損害賠償請求のリスクがあります。早急にプライバシーポリシーを整備し、社内規定を見直しましょう。
新機能を使いこなせない機会損失
LINEは継続的に新機能をリリースしていますが、多くの企業が活用できていません。特にLINEミニアプリは顧客体験を大きく向上させる可能性があります。
ミニアプリでは、ポイント管理、オンライン予約、会員証のデジタル化が可能です。リッチビデオメッセージやカルーセル形式の画像配信も、訴求力を高めます。
しかし、リッチメニューやクーポン機能すら十分に使いこなせていない企業が多いのが現状です。
新機能を効果的に活用するためには、定期的な情報収集を行い、小規模なテスト運用から始めることが重要です。成功事例を研究し、必要に応じて外部専門家の知見も活用しましょう。新機能を味方につけることで、競合との差別化が図れます。
AIツール活用の落とし穴
AIチャットボットは運用効率を向上させますが、適切に設定しないと顧客満足度を低下させます。よくある失敗として、回答精度が低く的外れな返答をしてしまうケース、不自然な会話になるケース、有人対応への切り替えがスムーズでないケースなどがあります。
効果的な活用には、AIの対応範囲を基本的な質問に限定し、複雑な質問は早めに有人対応に切り替えることが重要です。また、応答ログを定期的に確認し、継続的に改善することも必要になります。
AIであることを隠さず適切に開示することも大切です。成功企業では、簡単な質問はAI、複雑な問題は人間という役割分担で、効率性と満足度を両立しています。
AIは万能ではありません。人間との適切な連携により、真の価値を発揮します。
先人の失敗から学びLINE運用を成功させよう
LINE公式アカウントの運用において、失敗は決して珍しいことではありません。本記事で紹介した友だち獲得の困難さ、配信コンテンツの質の問題、顧客対応の落とし穴、データ活用の不足、そして新たな法規制への対応など、多くの企業が同じような課題に直面しています。
重要なのは、これらの失敗から学び、次の一手を打つことです。友だち獲得では魅力的な特典設計と積極的な声かけが必要です。配信では有益情報7割・販促3割のバランスを保ち、顧客対応では24時間以内の返信を心がけます。さらに、データ分析では定期的にKPIをチェックし、法的リスクを回避しながら新機能を積極的に活用していくことが求められます。
本記事で紹介した失敗事例と対策を参考に、まずは自社の運用を見直すことから始めてください。小さな改善の積み重ねが、必ず大きな成果につながります。先人の失敗を貴重な教訓として、LINE公式アカウントを成功へと導いていきましょう。
▼株式会社エフ・コードでは、「hachidori」を提供しています。
hachidoriは、配信設定やタグ設計はもちろん、施策の提案・改善まで専任担当がサポートする
“成果直結型のLINEマーケティング支援ツール”です。
まずは機能や活用事例についてまとめた、サービス資料をダウンロードしてみてください。

![[ロゴ] 株式会社エフ・コード](/assets/img/layout/header_title.svg)