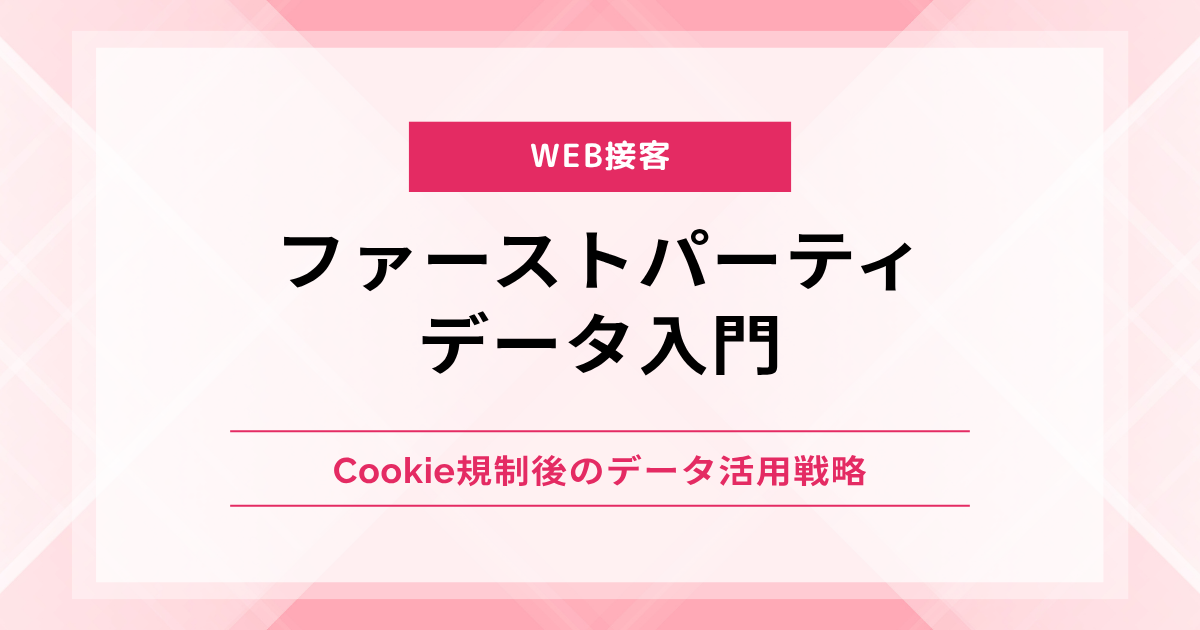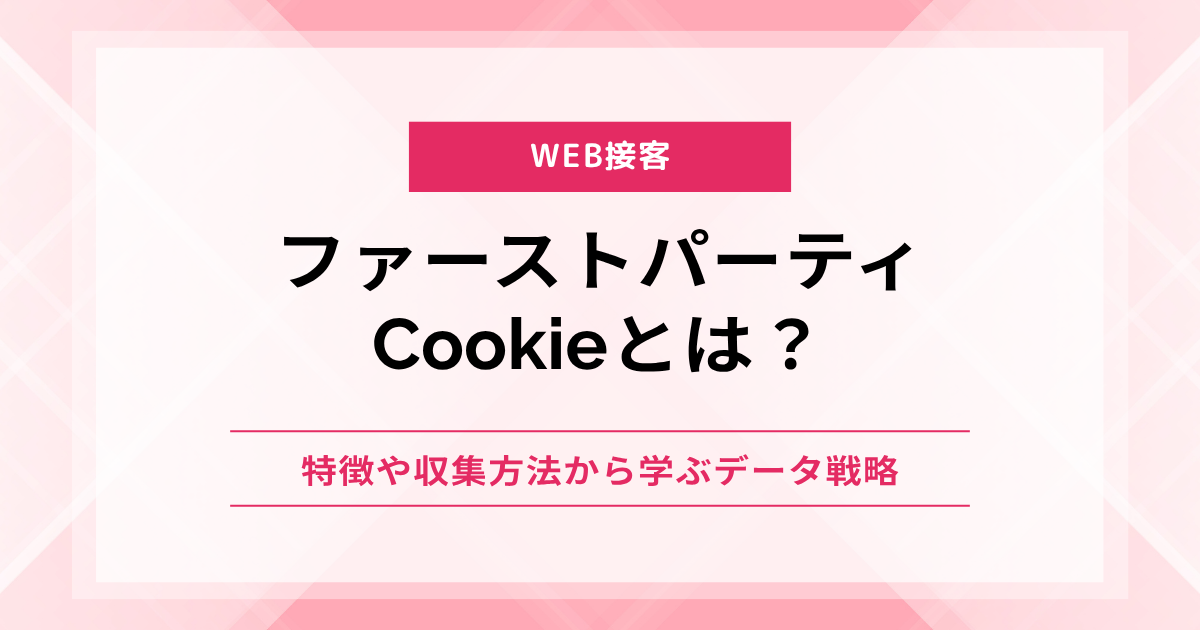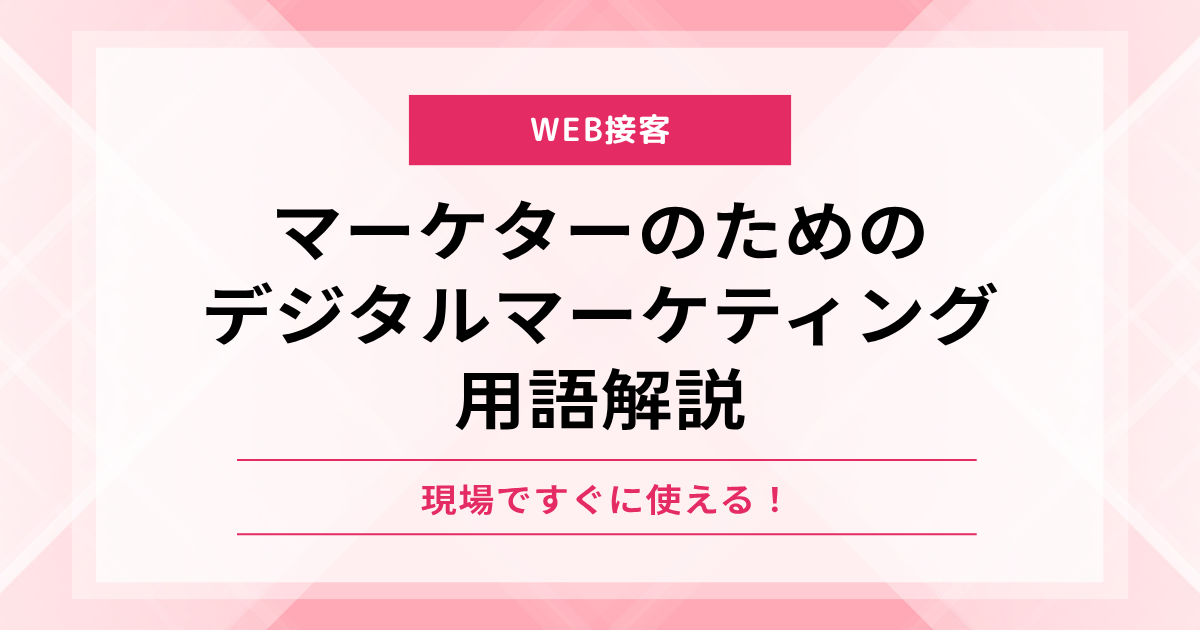デジタルマーケティングは大きな転換期を迎えています。Google ChromeによるサードパーティCookie規制の方針により、これまでのデータ活用手法の見直しが必要となっているのです。
このような変化の中で注目を集めているのが、企業が自社で直接収集する「ファーストパーティデータ」です。本記事では、ファーストパーティデータの基礎から実践的な活用方法まで、Cookie規制後の時代を見据えたデータ戦略について解説していきます。

データマーケティングの転換期を迎えて
デジタルマーケティングの世界で大きな転換点となるCookie規制。その影響と対応策について、現状を踏まえながら解説していきます。
Cookie規制の現状と影響
今後、Google Chromeでサードパーティ Cookieの段階的な廃止が始まる予定です。これは、デジタルマーケティングの手法に大きな影響を与える変更となります。
SafariやFirefoxなどの主要ブラウザでは、すでにサードパーティ Cookieの制限が始まっていましたが、シェア率約65%を占めるGoogle Chromeでの規制は、より大きな影響をもたらすことが予想されます。
サードパーティ Cookieは、これまでウェブサイトを横断した行動追跡やターゲティング広告の配信に活用されてきました。その利用が制限されることで、以下のような影響が考えられます。
- リターゲティング広告の効果減少
- ユーザー行動の追跡が困難に
- 広告効果測定の精度低下
データ活用戦略の見直しが必要な理由
Cookie規制は、プライバシー保護強化の世界的な潮流の一環です。日本でも2022年4月に改正個人情報保護法が施行され、Cookie情報の取り扱いに関する規制が強化されました。
このような状況下で、企業は以下の点からデータ活用戦略の見直しを迫られています。
1.プライバシー保護への対応
個人情報保護に関する規制は今後も強化されると見られ、より慎重なデータ取り扱いが求められています。
2.データ収集方法の変更
従来のような第三者を介したデータ収集が難しくなる中、自社でデータを収集・活用する仕組みの構築が必要となっています。
3.マーケティング手法の転換
これまでのような広範な行動追跡に基づくターゲティングから、より直接的な顧客とのコミュニケーションへの移行が求められています。
ファーストパーティデータへの期待
このような状況下で、企業が自社で収集・管理する「ファーストパーティデータ」の重要性が高まっています。ファーストパーティデータは、以下のような特長から、Cookie規制後の主要なデータソースとして期待されています。
- データの信頼性が高い
- 収集・活用の自由度が高い
- プライバシー保護の観点から安全
- 長期的な活用が可能
また、ファーストパーティデータの活用は、単なるデータ収集にとどまらず、顧客との直接的な関係構築にもつながります。これは、今後のデジタルマーケティングにおいて重要な要素となるでしょう。
デジタルマーケティングの新時代において、いかに質の高いファーストパーティデータを収集し、活用していくか。それが企業の競争力を左右する重要な要素となっていくのです。
ファーストパーティデータの基礎知識
Cookie規制の強化により注目を集めるファーストパーティデータ。その特徴やほかのデータとの違い、ビジネスにおけるメリットについて詳しく解説していきます。
ファーストパーティデータの特徴
ファーストパーティデータとは、企業が自社で直接収集した顧客データのことを指します。具体的には、自社Webサイトでの行動履歴、会員登録情報、購買履歴、アンケート回答、問い合わせ内容などが該当します。
最大の特徴は、データの出所が明確で、収集方法や目的の透明性が高いことです。自社と顧客との直接的なやり取りから得られる情報であるため、データの正確性と信頼性が高く、マーケティング活動に直接活用できます。
それぞれのデータの特徴と違い
デジタルマーケティングで活用されるデータには、以下のような種類があります。
ゼロパーティデータ
ファーストパーティデータの一種で、顧客が自発的に提供する情報です。例えば、アンケートの回答や、プロフィール設定での入力情報などが該当します。信頼性がもっとも高く、顧客の明確な意思や嗜好が反映されている点が特徴です。
セカンドパーティデータ
パートナー企業から提供される他社のファーストパーティデータです。例えば、メディア企業が持つ読者データや、ECサイトの購買データなどが該当します。データの質は高いものの、取得にはコストがかかります。
サードパーティデータ
データ専門会社や調査会社などの第三者が収集・提供するデータです。広範な情報を得られる一方で、データの精度や信頼性には注意が必要です。
ファーストパーティデータのメリット
ファーストパーティデータ活用の主なメリットとして、以下の点が挙げられます。
データの信頼性
自社で直接収集するため、データの質が高く、出所も明確です。
コスト効率
一度収集の仕組みを構築すれば、継続的なデータ収集が可能です。外部からのデータ購入と比べてコストを抑えられます。
プライバシー保護
顧客から直接同意を得て収集するため、プライバシー保護の観点からリスクが低くなります。
ファーストパーティデータがなぜ有効か
ファーストパーティデータは、現代のデジタルマーケティングにおいて特に重要な役割を果たします。その理由として、以下の点が挙げられます。
顧客理解の深化
直接的なデータ収集により、より正確な顧客像を描くことが可能です。効果的なマーケティング施策の立案につながります。
パーソナライゼーションの実現
個々の顧客の行動や嗜好を詳細に把握できるため、より適切な商品やサービスの提案が可能になります。
長期的な関係構築
データの継続的な収集と活用により、顧客との持続的な関係構築が可能になります。これは、顧客生涯価値(LTV)の向上にもつながります。
Cookie規制後の時代において、ファーストパーティデータの重要性はさらに高まることが予想されます。その特性を理解し、効果的に活用することが、今後のマーケティング成功の鍵となるでしょう。
ファーストパーティデータの収集と活用方法

データ収集の仕組みづくりから具体的な活用方法まで、実践的なアプローチを解説していきます。成功事例も交えながら、効果的なデータ活用のポイントを紹介します。
ファーストパーティデータの収集方法
ファーストパーティデータの収集は、オンラインとオフラインの両方のチャネルで行うことができます。それぞれの特徴を生かした収集方法を検討することが重要です。
オンラインでの収集方法
Webサイトやアプリケーションでのデータ収集には、以下のような手法があります。
- 1.トラッキングピクセルの設置:Webサイト内に1×1ピクセルの小さな画像を設置し、閲覧履歴やクリック行動などを追跡します。ユーザーの行動パターンを詳細に把握することが可能です
- 2.フォームによる情報収集:資料請求や会員登録、問い合わせフォームなどを通じて、直接的に顧客情報を収集します。この方法では、顧客の明確な意思のもとで正確な情報を得ることができます。
- 3.SNSを通じた情報収集:公式アカウントのフォロワーとのやり取りや、投稿へのリアクションなどから、顧客の興味関心を把握します。
オフラインでの収集方法
実店舗や対面でのコミュニケーションからも、貴重なデータを収集できます。
- 1.店舗での購買データ:POSシステムを通じた購買履歴の収集や、会員カードの利用データなどを活用します。
- 2.イベントでの情報収集:展示会やセミナーでのアンケート、名刺交換などを通じて、見込み客の情報を収集します。
効果的なデータ活用のために
収集したデータを効果的に活用するためには、以下のポイントに注意が必要です。
目的の明確化
データ収集を始める前に、どのような目的でデータを活用するのかを明確にします。目的に応じて、収集すべきデータの種類や分析方法も変わってきます。
データと価値の交換
顧客からデータを提供してもらう際は、それに見合う価値を提供することが重要です。例えば、会員特典やパーソナライズされたサービスなど、顧客にとって魅力的な特典を用意します。
継続的な改善
データの収集と活用は一度きりではなく、継続的な改善が必要です。定期的に効果を測定し、必要に応じて収集方法や活用方法を見直していきます。
ファーストパーティデータの活用の体制づくり
ファーストパーティデータを効果的に活用するには、適切な組織体制の構築が不可欠です。必要な人材の確保から、ツールの選定、プライバシー保護まで、実務的な観点から解説していきます。
必要な組織体制とリソース
ファーストパーティデータの活用には、全社的な取り組みが必要です。特に重要なのは、経営層のコミットメントと、部門を横断した協力体制の構築です。
データドリブンな組織文化を醸成するには、以下のような体制づくりが重要です。
データ活用専門部門の設置
企業規模に応じて、データ分析やマーケティングを専門とする部署を設置します。小規模な組織では、既存部門内にデータ活用のチームを設けることも検討できます。
部門横断的な協力体制
営業、マーケティング、カスタマーサポートなど、顧客接点を持つ部門間での情報共有と連携が必要です。データの収集から活用まで、一貫した取り組みができる体制を整えましょう。
求められる人材とスキル
ファーストパーティデータの活用には、多様なスキルを持った人材が必要です。それぞれの専門性を生かしながら、チームとして成果を上げていくことが重要です。
データサイエンティスト・アナリスト
データの収集・分析・解釈を担う中核的な存在です。統計手法やプログラミングの知識を生かし、データから価値のあるインサイトを導き出します。また、分析結果を分かりやすく可視化し、他部門にも理解しやすい形で提供する役割も担います。
マーケティングスペシャリスト
データ分析から得られた知見を実際のマーケティング施策に落とし込む専門家です。顧客理解を深め、最適なセグメンテーションを行い、ROIを意識した施策を立案・実行します。データドリブンなアプローチで、継続的な改善サイクルを回していきます。
テクニカルエンジニア
データ基盤の構築・運用を担う技術者です。システムの選定から導入、カスタマイズまでを一貫して管理します。また、セキュリティ面での知識も必要不可欠で、安全なデータ環境の維持に努めます。
データ管理ツールの選定
データ管理ツールは、ファーストパーティデータ活用の要となるシステムです。企業の規模や目的に応じて、適切なツールを選定することが重要です。
CRMシステム
顧客との関係性を管理する基幹システムとして機能します。顧客情報の一元管理、コミュニケーション履歴の記録、営業活動の支援など、幅広い機能を提供します。導入時は、既存システムとの親和性や、カスタマイズの自由度を重視して選定します。
CDPプラットフォーム
複数のデータソースから収集した顧客データを統合・管理するプラットフォームです。リアルタイムでのデータ処理や、高度なセグメンテーション機能を備えており、パーソナライズされたマーケティング施策の実現を支援します。
分析・可視化ツール
収集したデータを分析し、意思決定に活用するためのツールです。直感的な操作性と、充実したレポーティング機能を備えたものを選ぶことで、データ活用の民主化を促進できます。
プライバシー保護への対応
個人情報保護は、ファーストパーティデータ活用においてもっとも重要な課題の一つです。法令順守と顧客からの信頼獲得の両面から、適切な対応が求められます。
法的コンプライアンス
改正個人情報保護法に基づき、個人情報の利用目的の明示や同意取得を適切に行います。特に、Cookieなどの識別子の利用については、明確な説明と選択肢の提供が必要です。また、越境データ転送に関する規制にも注意を払う必要があります。
セキュリティ対策
データの収集から保管、利用に至るまで、包括的なセキュリティ対策を実施します。アクセス権限の厳格な管理や、データの暗号化、定期的なセキュリティ監査などを通じて、安全な環境を維持します。
透明性の確保
プライバシーポリシーを分かりやすく提示し、データの利用目的や保護方針を明確に説明します。また、顧客が自身のデータをコントロールできる手段を提供し、透明性の高い運用を心がけます。
これからのデータ活用で成功するために
デジタルマーケティングは大きな転換期を迎えています。Google ChromeによるサードパーティCookie規制は、多くの企業のマーケティング活動に影響を与えることが予想されます。しかし、この変化は同時に、より質の高いデータ活用への転換点ともなります。
ファーストパーティデータの活用は、単なるデータ収集にとどまりません。顧客との信頼関係を構築しながら、プライバシーに配慮した形で価値の高いデータを収集し、それを効果的なマーケティング施策へと結びつけていく――そんな包括的なアプローチが求められています。
そのためには、適切な組織体制の構築や、必要な人材の確保、ツールの導入など、さまざまな準備が必要となります。しかし、これらの投資は、より深い顧客理解と、効果的なマーケティング活動を実現するための必要不可欠な土台となります。
Cookie規制後の時代において、企業の競争力を左右するのは、いかに質の高いファーストパーティデータを収集し、活用できるかです。今こそ、自社に適したデータ活用戦略を構築し、実行に移すべきときなのです。
▼株式会社エフ・コードでは、WEB接客ツール「CODE Marketing Cloud」を提供しています。
以下のボタンから「CODE Marketing Cloud」の概要資料を無料でダウンロードいただけます。
「CODE Marketing Cloud」の主な特長は以下のとおりです。
・ユーザーのサイト内行動を分析した精度の高いWEB接客
・専門知識不要の様々な業界別接客テンプレート
・既にお使いのGoogle AnalyticsやMAツールとの連携
・ON/OFFテストやA/Bテストでの検証
各機能の詳細や導入に関するお問い合わせ、WEB接客関連のご相談もお気軽にお問い合わせください。
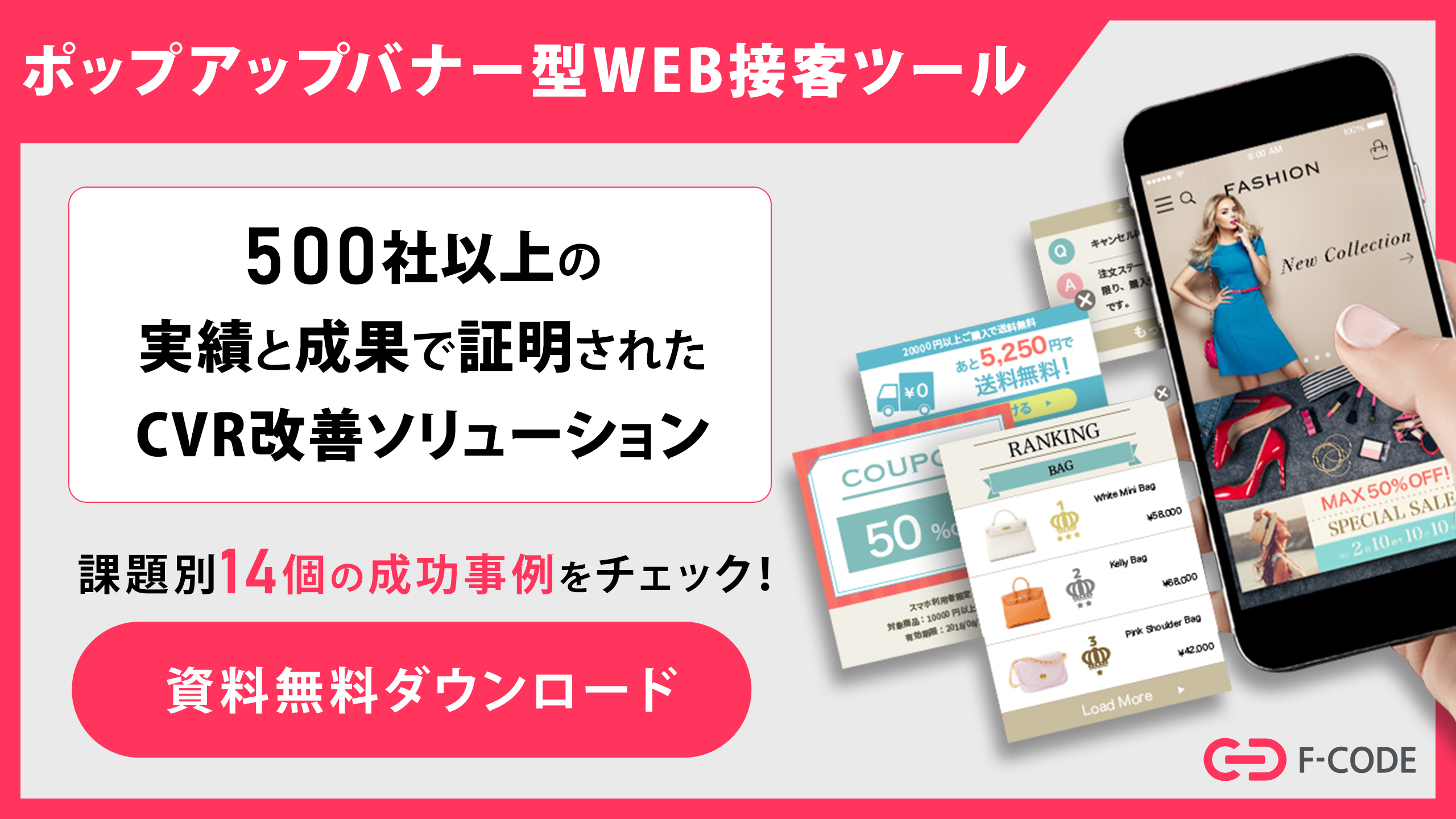
![[ロゴ] 株式会社エフ・コード](/assets/img/layout/header_title.svg)