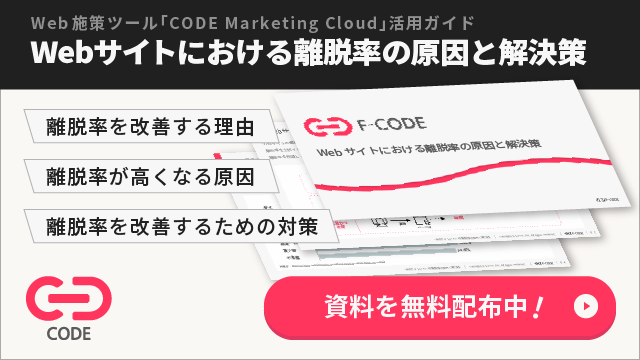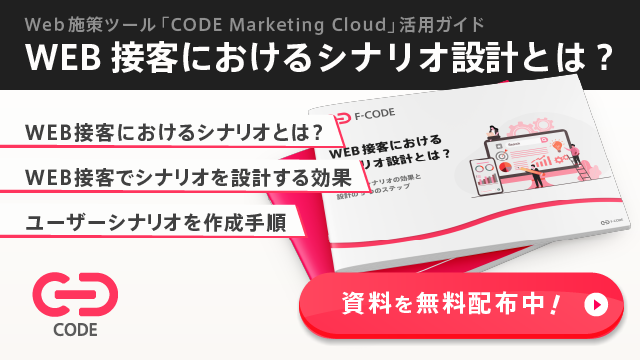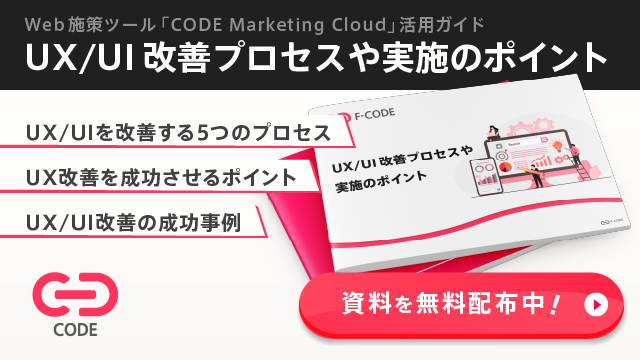CVRとは、Conversion Rate(コンバージョン率)の略で、Webサイトやアプリなどのデジタルメディアにおいて、訪問者が目的とする行動(購入や問い合わせなど)を行った割合を表す指標です。
CVRは、デジタルマーケティングの効果測定や改善に欠かせない重要な指標の一つです。
しかし、CVRの平均はどれくらいなのか、また、業界やデバイスによってCVRの平均は異なるのかがわからなければ自社のWebサイトのCVRの改善指標がわからず、適切な改善がかけられなくなってしまいます。
そこでこの記事では、CVRの平均値、基準値について、業界別やデバイス別に解説していきます。

CVRの平均は?業界別の基準値を解説

CVRの平均は1.82%
まず、CVRの平均値について見てみましょう。アメリカの企業であるContentsquareが2021年に調査したデータ「Digital Experience Benchmark」によると、日本のWebサイト・アプリのCVRの平均は1.82%という結果が出ています。
この調査は、日本を含む25か国、460億以上のユーザーセッションを対象にしたWebサイト・アプリのCVRを集計したものです。
この結果からわかることは、日本のWebサイト・アプリでは、100人中約2人が目的とする行動を行っているということです。
これは、国際的な比較では低い水準であると言えます。例えば、米国では2018年に発表された「E-commerce Conversion Rates 2018」によると、米国のEコマースサイトのCVRの平均は2.86%であり、日本よりも約0.84%高いです。また、欧州では2019年に発表された「E-commerce Benchmark KPI Study 2019」によると、欧州のEコマースサイトのCVRの平均は1.85%であり、日本よりも約0.03%高いです。
このように、日本ではCVRが低い傾向にあることがわかります。しかし、これは日本全体で見た場合であり、業界やデバイスによってはCVRが高い場合もあります。
次に、業界別やデバイス別にCVRの平均値を見てみましょう。
業界別のCVRの平均
次に、業界別にCVRの平均値を見てみましょう。株式会社ユニリーバが発表した調査では、以下のような業界別のCVRの平均値が出ています。
- Eコマース:2.04%
- メディア:1.29%
- サービス:1.67%
- ファイナンス:2.08%
- その他:1.77%
この結果からわかることは、Eコマースやファイナンスといった業界ではCVRが高く、メディアといった業界ではCVRが低いということです。これは、業界ごとに目的とする行動や訪問者の意図が異なることが影響していると考えられます。
例えば、EコマースやファイナンスのWebサイト・アプリでは、訪問者は購入や申し込みといった明確な目的を持って訪れることが多いため、CVRが高くなる傾向にあります。
一方、メディアのWebサイト・アプリでは、訪問者は情報収集や娯楽といった目的で訪れることが多く、必ずしも行動を行う必要がないため、CVRが低くなる傾向にあります。
また、業界ごとにCVRの平均値には幅があります。
例えば、Eコマースの業界では、最高値は5.77%であり、最低値は0.01%です。これは、Eコマースの業界には様々なジャンルやカテゴリーが存在し、それぞれに特徴や競合が異なることが影響していると考えられます。
例えば、ファッションやコスメといったジャンルでは、訪問者の購買意欲やブランド力が高いことがCVRを上げる要因になることもありますが、家電や家具といったジャンルでは、訪問者の比較検討や価格感度が高いことで「実際に物を手に取ってみたい!」「実際に目で見て確かめてみたい」という、積極的な商品毛等の気持ちが、CVRを下げる要因になってしまうこともあります。
このように、業界別にCVRの平均値は異なります。自社のWebサイト・アプリのCVRを改善するためには、自社の業界のCVRの平均値を参考にしつつ、自社のジャンルやカテゴリーの特徴や競合状況を考慮することが重要です。
デバイス別のCVRの平均
最後に、デバイス別にCVRの平均値を見てみましょう。株式会社ユニリーバが発表した調査では、以下のようなデバイス別のCVRの平均値が出ています。
- PC:2.16%
- スマートフォン:1.61%
- タブレット:1.86%
この結果からわかることは、PCでのCVRが最も高く、スマートフォンでのCVRが最も低いということです。
これは、デバイスごとに訪問者の行動パターンや利用シーンが異なることが影響していると考えられます。例えば、PCでの訪問者は、仕事や学習などで集中してWebサイト・アプリを利用することが多く、目的意識が高いため、CVRが高くなる傾向にあります。
一方、スマートフォンでの訪問者は、移動中や暇つぶしといったシーンでWebサイト・アプリを利用することが多く、目的意識が低い可能性があるため、CVRが低くなる傾向にあると言われています。
また、デバイスごとにWebサイト・アプリの表示や操作性が異なることも影響しています。例えば、PCでのWebサイト・アプリでは、画面サイズが大きく情報量が多く見やすいことや、キーボードやマウスで操作しやすいことがCVRを上げる要因になります。
▼下記の資料では、CVRの改善に欠かすことのできない、Webサイトを離脱する主な原因とユーザーに満足してもらうためのサイト構造をわかりやすく解説しています。
・離脱率の改善方法
・UX/UIの観点から見るサイト回遊を高める方法
・Webサイトの回遊率を高めるためのおすすめツール
「Webサイトの回遊性を上げたい」や「Webサイトの離脱率を改善したい」とお考えの方は、ぜひダウンロードしていただき、自社サイトの改善にお役立てください。
CVRの計算方法は?

CVRの計算方法は、以下の式で求めることができます。
CVR(%) = コンバージョン数 / サイト訪問者数 × 100
例えば、サイトに1000人が訪れて、そのうち50人が商品を購入した場合、CVRは5%となります。
自社サイトのCVRの平均はどれくらいが良い?
業界や業種、売るべき商品によって平均となるCVRは異なるため、自社サイトのCVRの平均はどれくらいが良いかという基準は一概には言えません。
しかし、一般的には、CVRが高いほどサイトのパフォーマンスが良いと言えます。CVRを高めるためには、ユーザーのニーズやペルソナを分析し、サイトのデザインやコンテンツ、ユーザーに対するサイト上のナビゲーションなどを最適化する必要があります。
自社サイトのCVRを設定する際には、達成したい目的・目標から逆算したCVRの設定が重要となります。
自社のWEBマーケティングのKPIによって目標にするCVRは変わる
自社のWEBマーケティングのKPIによって、CVRの重要度も変わってきます。例えば、ブランディングや認知度向上を目的としたサイトでは、CVRよりもPVや滞在時間などの指標が重視されるでしょう。
一方、ECサイトやリード獲得型のサイトでは、CVRが直接売上や利益に影響するため、最優先で改善すべき指標となります。
このように、CVRは自社サイトの成果を測るために欠かせない指標ですが、それだけでは十分ではありません。他の指標と併せて分析し、サイト全体の最適化を行うことが重要です。
▼下記の資料では、WebサイトのCVRを改善するために必須となる、シナリオ設計のやり方をわかりやすく解説しています。
・Web接客におけるシナリオとは?
・Web接客でシナリオ設計する理由や効果
・Web接客のシナリオ設計手順
デジタルマーケティングにおける顧客対応がますます重要性を増している今、Web接客を導入しようとお考えの方は、ぜひ下記の資料をダウンロードしていただき、自社サイトの改善にお役立てください。
自社サイトの特性に合ったCVRを導き出す
CVR(コンバージョン率)の適正値は、業界や商材によって異なります。そのため、単純な数値の比較ではなく、自社の特性を考慮した目標設定が必要です。
具体的には、以下のような要素を考慮しながら、自社に適したCVR目標を設定しましょう。
- 商品やサービスの単価帯
- 商談や成約までのリードタイム
- 顧客の購買決定プロセス
- 競合状況と市場環境
例えば、高額なB2Bサービスの場合、CVRは0.1%程度でも十分な成果が見込めます。一方、日用品のECサイトでは、3%以上のCVRが期待できるでしょう。
自社の過去データと業界事例を比較分析すれば、現実的な目標値を設定できるでしょう。まずは直近の実績を基準に、段階的な改善目標を立てることをおすすめします。
CVRが平均より低い場合の主な原因5つ
自社のCVRが業界平均を下回る原因は、多くの場合で複数の要因が絡み合っています。継続的に改善するためには、まず原因を正確に把握する必要があります
。
ここでは、CVR低下の主な原因として挙げられる5つのポイントを、具体的な対策とともに解説します。
顧客が離脱するポイントを特定できていない
顧客の離脱ポイントを特定できていないことは、CVR低下の要因の一つです。特に「自社視点の施策」と「顧客行動の分析不足」の2つの問題が、離脱ポイントの特定を妨げています。
自社視点の施策が招く問題として、企業側の都合を優先したWebサイト設計が挙げられます。例えば、商品の特徴や機能を細かく説明しても、顧客が求める課題解決の視点が欠けていれば、離脱を招くでしょう。
顧客行動の分析不足による影響も見逃せません。アクセス解析ツールで確認できる定量データだけではなく、問い合わせ内容やカスタマーサポートへの質問など、定性データの分析も大切です。
具体的な対策としては、ユーザーテストやヒートマップ分析を活用し、実際の行動データを収集します。そのデータを基に、ファネルファネル分析で段階ごとの離脱率を確認し、改善が必要なポイントを特定していきましょう。
ターゲット設定が不十分である
不適切なターゲット設定は、CVR低下の根本的な原因につながります。商品やサービスの価値が、想定する顧客層のニーズと合致していなければ、いくら施策を実施しても効果は限定的です。
例えば、20代向けのサービスを40代にアプローチしたり、個人向け商品を法人に販売しようとしたりすれば、CVRが低下するのは当然でしょう。顧客層の選定ミスは、広告費用の無駄遣いにもつながります。
適切なターゲット設定のためには、以下のポイントを確認しましょう。
- 既存顧客の属性分析
- 競合他社のターゲット層
- 商品・サービスの価格帯に見合う所得層
- 潜在顧客のペルソナ設定
現状のターゲット層を見直し、商品やサービスの特性に合った顧客層を再設定すれば、CVRの改善が期待できるでしょう。
競合施策に負けている
競合他社の施策に負けていることも、CVR低下の要因の一つかもしれません。特に価格や機能で差別化が難しい商品・サービスの場合、競合との比較検討で顧客を失うケースが多くなります。
競合分析では、以下のような観点での比較が効果的です。
- 価格設定と販売方式
- 商品・サービスの特徴
- LP(ランディングページ)の構成
- 顧客サポート体制
例えば、競合が無料トライアルを提供しているのに対し、自社は有料デモのみの場合、顧客は競合を選択する可能性が高まります。競合の方が商品説明やサポート体制が充実していれば、安心感の面で劣ることになるでしょう。
改善のためには、定期的な競合分析と自社の強みの明確化が必要です。競合と同じ土俵で勝負するのではなく、自社ならではの価値を効果的に訴求する方法を考えましょう。
市場トレンドを見誤っている
市場トレンドの見誤りは、CVRに大きな影響を与えます。季節変動や新しい市場動向への対応が遅れることで、顧客ニーズとのズレが生じてしまいます。
見逃しやすい市場トレンドには、以下のようなものがあります。
- 季節イベントに応じた需要変化
- 競合他社の新サービス登場
- SNSでの話題変化
- 技術革新による顧客ニーズの変化
例えば、夏物商品の展開が遅れたり、スマホ決済対応が不十分だったりすると、顧客は競合サイトへ流れてしまうでしょう。また、SDGsやサステナビリティなど、新しい価値観への対応も大切です。
トレンドを把握するには、Google Trendsやソーシャルリスニングツールの活用が効果的です。定期的なトレンド分析を行い、機動的な対応ができる体制を整えましょう。
広告媒体を適切に活用できていない
不適切な広告媒体の選択は、CVR低下につながります。ターゲット層が利用しない媒体へ出稿しても、コストが増大するばかりです。
効果的な広告運用には、以下のポイントが大切です。
- ターゲット層の利用媒体分析
- 各媒体の費用対効果測定
- クリエイティブの媒体別最適化
- 配信時間帯の調整
例えば、若年層向け商品なのにFacebookのみの出稿や、スマホユーザーが多いのにPC向け広告が中心では、効果は限定的です。各媒体の特性を理解し、適切な配信設定を行いましょう。
定期的な広告効果の測定と、配信設定の見直しが必要です。特に検索広告とディスプレイ広告では、求められる施策が異なります。
CVRの上げ方・改善方法|3つ

以下では、CVRの上げ方・改善方法について3つのポイントをご紹介します。
1. CTAの数を増やす
CTA(コール・トゥ・アクション)とは、ユーザーに対して行動を促すボタンやリンクのことです。例えば、「今すぐ購入」「無料相談」「詳細はこちら」などがCTAにあたります。CTAは、ユーザーに次のステップを示し、コンバージョンに近づける役割を果たします。
しかし、CTAが少ないと、ユーザーはどこに進めばいいのか分からず、離脱してしまう可能性が高くなります。そのため、CVRを上げるためには、CTAの数を増やすことが有効です。ただし、CTAの数を増やすだけでは不十分です。
CTAは、ユーザーのニーズやページの目的に合わせて配置する必要があります。また、CTAの文言やデザインも工夫することで、クリック率を高めることができます。
2.ターゲットと検索意図にあった情報を提供する
CVRを上げるためには、Webサイトに訪れたユーザーが求めている情報を提供することが重要です。しかし、ユーザーは一様ではありません。
同じキーワードで検索しても、ユーザーの属性や目的は異なる場合があります。そのため、ターゲットと検索意図にあった情報を提供することで、ユーザーの満足度を高めることができます。
例えば、「スマートフォン」で検索したユーザーは、「スマートフォンの特徴や比較」「スマートフォンの購入方法やお得なプラン」「スマートフォンの使い方やトラブル対処法」など、様々な情報を求めている可能性があります。
その場合、Webサイトでは、「スマートフォン」に関する幅広い情報を提供するだけでなく、「初心者向け」「上級者向け」「ビジネス向け」など、ターゲット別に情報を分類することで、ユーザーが自分に合った情報を見つけやすくすることができます。
3.CVポイントを変更する
CVポイントとは、Webサイト上でコンバージョンが発生する場所のことです。例えば、「カートに入れる」「購入手続きへ進む」「送信する」などがCVポイントにあたります。CVポイントを変更することで、CVRを上げることができる場合があります。
例えば、ユーザーがコンバージョンに至るまでに、多くのステップを踏まなければならない場合、ユーザーは途中で挫折してしまう可能性があります。その場合、CVポイントを早めに設定することで、ユーザーの負担を減らすことができます。
逆に、ユーザーがコンバージョンに至るまでに、十分な情報や信頼感を得られない場合、ユーザーは不安に感じてしまう可能性があります。
その場合、CVポイントを遅らせることで、ユーザーに安心感を与えることができます。CVポイントを変更する際には、ユーザーの行動やフィードバックを分析することで、最適なタイミングを見極めることが重要です。
▼下記の資料では、CVRの改善に欠かすことのできない、UX/UI改善のプロセスや実施ポイントをわかりやすく解説しています。
・UX/UIを改善するプロセス
・UX改善を成功させるポイント
・UX/UI改善の成功事例
デジタルマーケティングにおける顧客対応がますます重要性を増している今、UX/UI改善の改善が必要不可欠です。もし「UX改善の具体的なプロセスが分からない」や「考え方や改善のポイントを詳しく知りたい」とお考えの方は、ぜひ下記の資料をダウンロードして、自社サイトの改善にお役立てください。
スピーディーなCVRの改善にはWEB接客ツールがおすすめ
この記事ではCVRの平均値から、CVRの上げ方・改善方法について3つのポイントをご紹介しました。
これらのポイントを実践することで、Webサイトの効果を高めることができます。しかし、CVRの改善は一朝一夕にはできるものではありません。
Webサイトの改善には時間や労力がかかりますし、効果の検証も必要です。そこで、スピーディーなCVRの改善にはWEB接客ツールがおすすめです。WEB接客ツールとは、Webサイト上でユーザーとコミュニケーションを取ることができるツールのことです。
例えば、「チャット」「ポップアップ」「バナー」などがWEB接客ツールにあたります。WEB接客ツールを利用することで、以下のようなメリットがあります。
- ユーザーのニーズや疑問に即座に応えることができる
- ユーザーにパーソナライズされた情報やオファーを提供することができる
- ユーザーの行動や属性に応じて最適なCTAを表示することができる
- Webサイトの改善や検証にかかる時間やコストを削減することができる
WEB接客ツールは、CVRの上げ方・改善方法を効率的かつ効果的に実現するための強力な武器です。ぜひ、WEB接客ツールを活用して、Webサイトのパフォーマンスを向上させてください。
▼株式会社エフ・コードでは、WEB接客ツール「CODE Marketing Cloud」を提供しています。
以下のボタンから「CODE Marketing Cloud」の概要資料を無料でダウンロードいただけます。
「CODE Marketing Cloud」の主な特長は以下のとおりです。
・ユーザーのサイト内行動を分析した精度の高いWEB接客
・専門知識不要の様々な業界別接客テンプレート
・既にお使いのGoogle AnalyticsやMAツールとの連携
・ON/OFFテストやA/Bテストでの検証
各機能の詳細や導入に関するお問い合わせなど、お気軽にご相談ください。
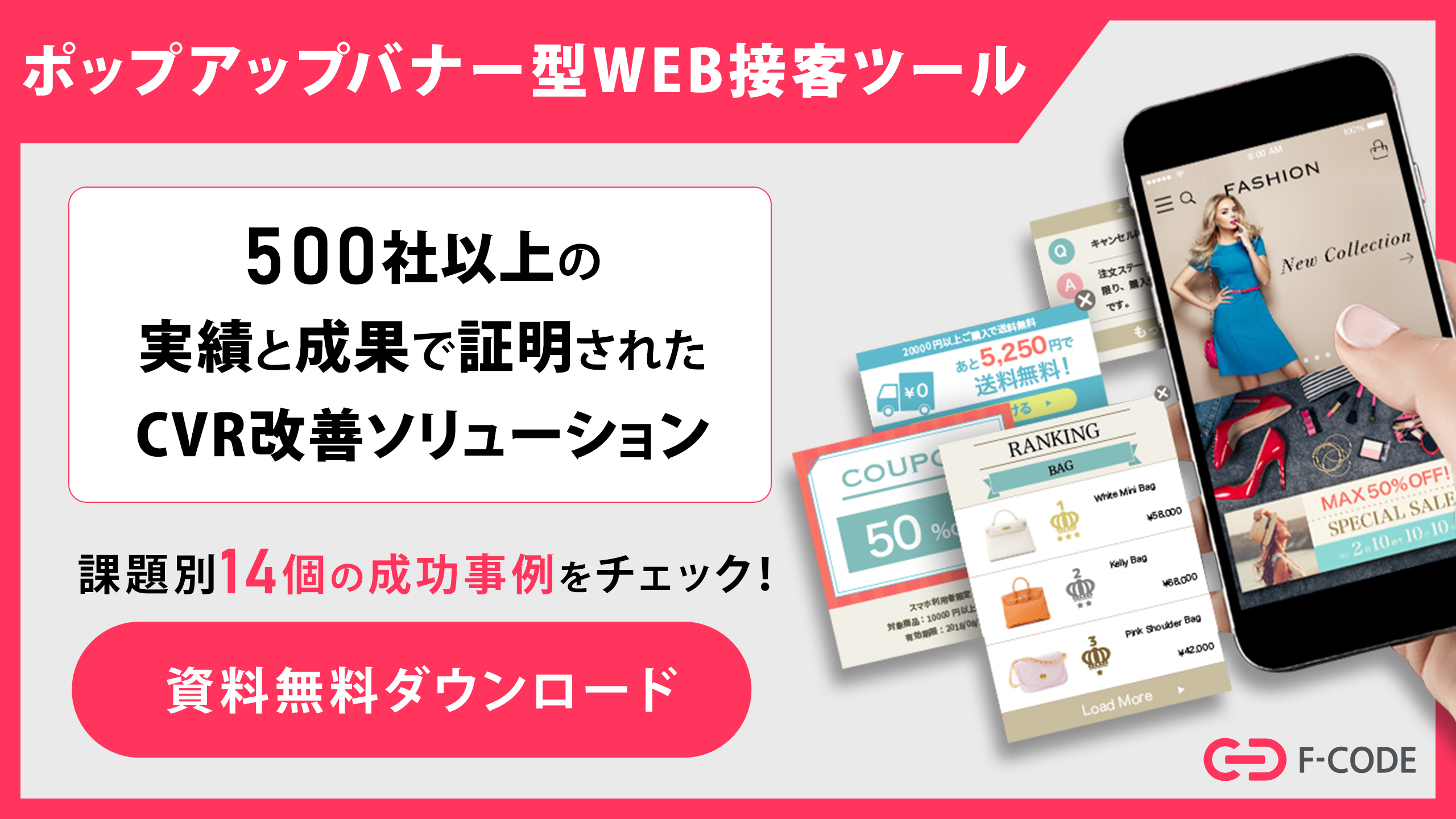
![[ロゴ] 株式会社エフ・コード](/assets/img/layout/header_title.svg)